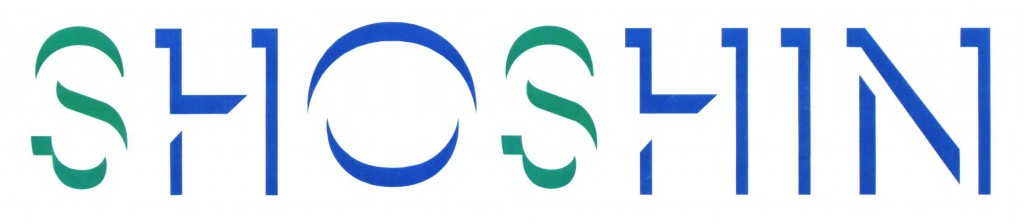県内の公立中高一貫校は5校あります。県立相模原中等教育学校、県立平塚中等教育学校、横浜市立南高校附属、横浜市立サイエンスフロンティア、川崎市立川崎高校附属です。設立当初は県立相模原中等教育学校などは受検倍率が15倍ほどあり、大変な騒ぎになっていましたが、今ではその数字も落ち着きを見せ、6倍前後となっています。それでも私立中学とは違い、この数値が実倍率なので相変わらず厳しい状況であることには違いありません。
当教室での2025年度の授業も始まり、落ち着きが見られたところで、遅ればせながら今春行われた県立中等教育学校の適性検査をじっくり確認しました。
まず、県内の適性検査はⅠとⅡに分かれており、各300点満点、計600点満点となっています。今回の適性検査Ⅰでは、問1は久地円筒分水を題材に、問2は熱中症予防を題材に、問3はトラックによる輸送を題材に、問4は校外学習を題材に会話文や資料を読み取り、科学・論理的思考力及び社会生活実践力の基礎的な力をみることを狙いとした内容が出題されました。そして、問5ではかつて行われていたグループ活動に類似した内容で、学級活動を題材に、卒業生に向けて自分たちができる活動について自分の考えをまとめ、文章で適切に表現するという内容が盛り込まれていました。ここ数年70字~80字以内でまとめ上げるものとなっています。
適性検査Ⅱでは、問1で日本語のかなを題材に、問2で林業を題材に、問3で調理実習を題材に、問4で立方体を題材に会話文を読んだり、資料の内容を読み取ったりしながら、科学・論理的思考力や表現コミュニケーション力を試されたりする内容となっています。問1の日本語のかなに関しては、NHKの大河ドラマ「光る君へ」が放送されていたので題材として取り上げられたのかもしれませんね。
適性検査Ⅰ・Ⅱを通して言えることは、一つ一つが時間がかかるものが多く、各45分の時間内でこれらの内容と向き合いことは中々難儀であるということです。国語力がなくては何が書かれているか分かりませんし、計算力がなければ時間がかかってしまって時間内に解ききれないことも考えられます。いくつかの資料を見て計算したり、考えたりしなければならないので分析力であったり、処理能力なども必要になるでしょう。そして、70字~80字以内にまとめ上げなければならない学級活動を題材にしたものなどは普段の生活から培われたものが土台にないと短い時間でしっかりしたものをまとめあげることはかなり難しいことだと思いました。
いずれにしても、短い時間で様々な能力が試される適性検査は、一通り解いてみて改めて手強いものだと感じました。公立中高一貫校を志望されている児童の皆さん、過去問を中心に取り組み、全力で対策に当たっていただきたいと思います。(二宮)
分かるまで教える、身につくまで学べる、親身の指導
SHOSHINからのお知らせ
- HOME »
- SHOSHINの窓辺(スタッフによるブログ) »
- 受験 »
- 県立中等教育学校の適性検査