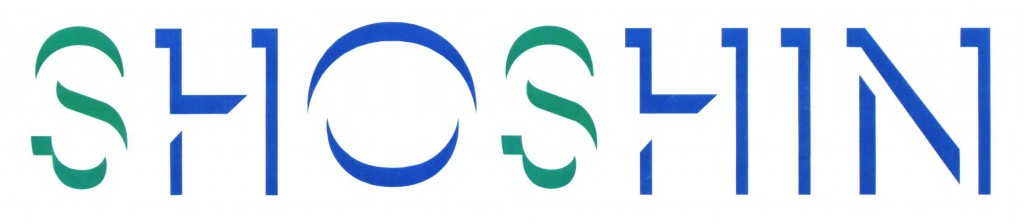相模女子大学中学部の学校説明会に参加してきました。今回の内容の中心は学校の教育活動について、大学合格実績について、来年度入試についてでした。
まず初めに、中学部と高等部で校長をそれぞれ分けて学校運営を行っていくというものでした。そこで、新校長から教育活動について様々な話がありましたが、メインは非認知能力を養成していくことに重きをおくというものでした。学校側が捉える認知能力とは模試の試験結果(偏差値や順位)だとか学校の成績(評定)など見える学力を差します。それに対して、非認知能力とは、論理的思考力や創造力、知的好奇心やコミュニケーション能力、忍耐力など見えない能力のことを差します。
この非認知能力の育成にあたり、「プロジェクトアドベンチャー」「アサーショントレーニング」「マーガレットリフォーム」の三本柱で取り組みを行っているということでした。「プロジェクトアドベンチャー」では、グループ活動を通じて他者意識を高め、成功体験から成長の気づきを得るというものです。「アサーショントレーニング」では、自分も相手を尊重しながらコミュニケーション能力を育成していくというものです。そして、「マーガレットリフォーム」は生徒主体による校則ルールの見直しなど皆で納得解を作っていくというものだそうです。私もしっかり説明を伺いましたが、ご興味のある方は学校に足を運んでみてはいかがでしょうか。個人的には内容は興味深いものでした。
大学合格実績については医学部医学科に3名の合格者が出すなど例年以上の結果を得たそうです。指定校推薦枠はご近所の北里大学に9つの枠を確保している他、総合大学、理工・医療系、女子大など全部で400近い枠を有しているそうです。中高一貫生の大学合格結果では、一般選抜入試、総合型選抜入試を中心に大健闘しているというデータも添えられていました。ただ、指定校推薦については高入生の方が利用割合が多く、評定を上手く取れているという見方はあるとは思いますが、別の解釈として、中高一貫生の方が積極的に一般受験をするチャレンジングな傾向があるのは、学校側の非認知能力育成の取り組みを長く受けている生徒の強みと考えて良いのではないかと思いました。
2026年度入試に関しては多少の変更点はありますが、日程としては次のとおりです。
[教科型入試]第1回 2/1午前2科、第2回 2/1午後2科・4科、第3回 2/2午後2科・4科、第4回 2/5午前2科
[適性検査型入試]2/1午前
[プログラミング入試]第1回 2/1午前、第2回 2/5午前
複数回受験では「いいとこ取り」のメリットがあります。2科・4科選択の場合は4科受験の方が合否判定のシステム上有利だと思います。
特待生制度では、教科型は得点率75%以上、適性検査型では得点率上位20%の入学者に対して、入学金相当額の給付を受けることができるそうです。
直近の説明会は、6/7に入試体験会(9:30~11:00)が、6/28に学校説明会(9:30~11:30)が、9/20に適性検査型入試体験会&説明会(14:00~16:00)が開催予定です。詳しくは学校のホームページ等でご確認ください。(二宮)
分かるまで教える、身につくまで学べる、親身の指導
SHOSHINからのお知らせ
- HOME »
- SHOSHINの窓辺(スタッフによるブログ) »
- 受験 »
- 相模女子大学中学部説明会