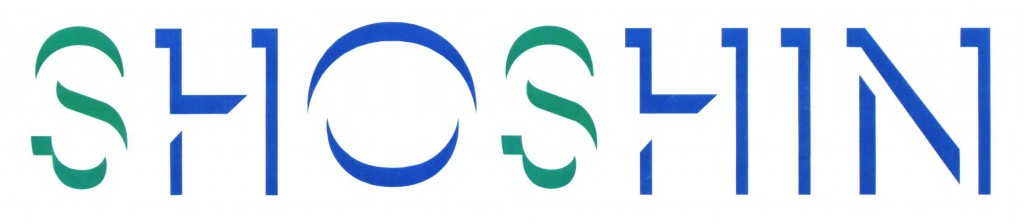2月14日に行われた公立高校入試の理科の問題分析を掲載します。分析は榎原です。
問題構成は従来通りの大問が8問でした。そのうち前半の4問は各分野毎の雑問形式、後半4問がそれぞれの分野での実験や観察についての問題となっていて、その配点も前半36点、後半64点と、ここ数年全く同じでした。
出題分野を見てみると、各学年で学習する内容が、満遍なく出題されています。配点で見ると、中1内容が25点分、中2内容が31点、中3内容が44点となっていますが、学年による配点は年によってばらつきがあります。ただし、後半の問題で採り上げられた学年の単元からは、前半の雑問形式での出題は見られないので、全学年の学習範囲から広く出題しようとする意図が窺えます。
個人的な感想ですが、出題のレベルは例年とほぼ同等だったと思います。中には易しくなったと思われる出題もありました。前半の物理分野の雑問形式の中の問題です。2本の電熱線に加えた電圧と流れた電流のグラフが与えられていて、「どちらが抵抗が大きいか」「抵抗は何オームか」という設問でした。「オームの法則」を学習した際の例題レベルの問題でした。後半の化学分野の設問でもデータがプロットされたグラフが与えられているので、これにちょっと手を加えれば、過不足なく反応する量などを容易に推定することが可能でした。これに気づけば、細かな計算を避けて、はるかに早く選択肢を選ぶことができたと思います。ただし、このことに気づかなければ、グラフからデータを読みとりにくいこともあって、手を焼いた受験生も多かったかもしれません。最後の地震に関する出題でも、地震計の記録や地震波の伝わり方のグラフをうまく利用できれば決して難しい問題ではないのですが、そのあたりの練習を積んでおかなければ正答は容易ではなかったかもしれません。受験に向けて前半の基礎的な内容への対応に加えて、後半での応用力を積んでおくことが必要とされているのでしょう。
集計後の結果を見てみなければ確かなことは言えないが、平均点は例年並みとなるのではないかと予想します。
以下、設問毎の内容と履修学年を掲載します。
問1 物理分野雑問
(ア)凸レンズと光の進み方[1年] (イ)電流のはたらき[2年] (ウ)静電気[2年]
問2 化学分野雑問
(ア) 物質と密度[1年] (イ) 電解質とイオン[3年] (ウ) 中和反応とイオン[3年]
問3 生物分野雑問
(ア) 顕微鏡の使い方[1年] (イ) 動物の分類[2年] (ウ) 血液の循環[2年]
問4 地学分野雑問
(ア) 空気中の水蒸気[2年] (イ) 太陽系の惑星[3年] (ウ) 昼夜の変化[3年]
問5 運動とエネルギー[3年]
斜面と水平面が連続したコース上を動く小球の運動についての問題です。速さを計算する問題も出題されていますが、結果の表の一部が空欄として与えられていて、これを埋めていくことで対応できるようになっています。
問6 化学変化と物質の量[2年]
発泡入浴剤として使われている、炭酸水素ナトリウムとクエン酸を使った化学反応に関する問題です。反応量や濃度の計算が含まれていて、やや難しい問題といえるでしょう。データがプロットしあるグラフをうまく使えば、ややこしい計算を回避することができますが、こうした問題に対する練習量が必要となるでしょう。
問7 分解者のはたらき[3年]
土の中の微生物のはたらきに関する実験の問題です。ヨウ素反応やベネジクト反応の結果から、実験結果に対する考察を、生徒と先生の会話形式で進めていく形式になっています。こうした対話文の問題は必ず出題されています。
問8 大地の変化[1年]
この単元の雑問形式といえる問題でした。(ア)は日本の地下のプレートの様子を問う問題。(イ)は地震計のしくみについての問題。(ウ)は地震計の記録から簡易的な地図上で震央の位置を選ぶ問題でした。初期微動継続時間と震源距離が比例することから考える問題です。「○km」と具体的な数値を求める問題でないことがかえって受験生には難しく感じられたかもしれません。またその後の小問も、地震計の記録や地震波の伝わり方のグラフを利用して解く問題となっています。こちらは緊急地震速報と主要動との時間の差を求める問題でした。(榎原)
分かるまで教える、身につくまで学べる、親身の指導
SHOSHINからのお知らせ
- HOME »
- SHOSHINの窓辺(スタッフによるブログ) »
- 塾 »
- 公立高校入試問題分析~理科