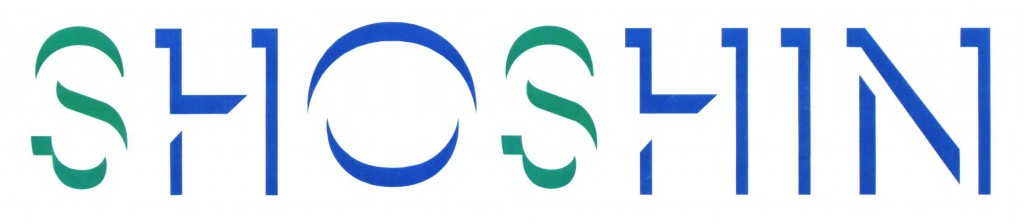森鴎外の「高瀬舟」は中学三年生の教科書に掲載されている定番作品の一つです。そこには安楽死や社会的な地位の差異がテーマとして取り上げられています。この話の最後に同心である羽田庄兵衛は喜助の犯した罪(苦しむ弟を救ってあげたいと思い取った行動によって弟は死んでしまう。)は果たして罪と呼べるものなのか、自分での判断を保留し、お奉行様(権力者)の判断を自己の判断として納得させようとしています。このことは、一介の同心と言えども、奉行側の人間であるはずの庄兵衛がお上の判断に疑義を持っていることの表れに受け止めることができます。ここに自身も高級官僚であった鴎外のバランス感覚の良さを感じます。庶民との価値観の相違が有っては気づくことのできない視点だと思います。
鴎外の別の小説「最後の一句」の中で、主人公である娘が、不正を働き処刑の決まっている父を助けるために奉行所へ父の助命の嘆願書を差し出す場面で、奉行から「嘆願の内容では父の命を救う代わりに、お前たち子供は4人揃って死罪になるかもしれない。」とお白州で厳しい取り調べを受けている娘が最後に「それでも構いません。お上が決めることに間違いはありません。」ときっぱりと言い放ちます。この娘の一言にお奉行は恐怖を感じ、結果として娘の望みが叶うことなります。この場面でも鴎外が庶民の持つ強さやしたたかさなどを十分に認知していたことが窺えます。
違う作品から共通する事項を見つけ出すと筆者の思考の一端に深く触れたことが出来たようでもう一つの読書の楽しみを享受したような気がします。いずれにせよ、世の中がよく見えていたからこそ数々の名作を世に出すことができたのではないでしょうか。(吉川)
分かるまで教える、身につくまで学べる、親身の指導
SHOSHINからのお知らせ
- HOME »
- SHOSHINの窓辺(スタッフによるブログ) »
- 塾 »
- 読書は楽しい